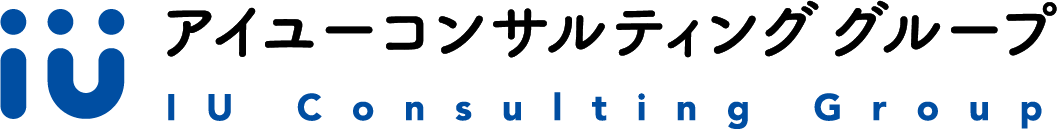| 相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
|---|---|---|
| 1.不動産 2.定期預金 3.株式 |
姪A 甥B 甥Cの3名 |
・自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし) ・甲金融機関が解約に応じない。 ・相続税申告の期限に間に合わない。 |
事例ケース
このケースの問題点
自筆証書遺言が2通ある場合、原則は直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。
そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続することになった姪Aの間で喧嘩が起こりました。
また、解約に応じない甲金融機関への訴訟も検討する必要がありました。
なお、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書で遺産の全部を特定の者に相続させようとした場合、遺留分の問題は生じません。
さらに、相続税の法定申告期限(相続開始から10ヶ月)が迫っており、期限までに遺産相続の手続きが終わらない可能性が出てきました。
このケースの解決事例
遺言状は新しい日付のものが有効とされますので、新しい遺言状に沿って執行手続きを行います。(相続手続完了までの期間:約9ヶ月)
【1】「遺言書の検認」を行う。(検認の手続は約1ヶ月を要する。)
↓
【2】検認の手続が完了後、「遺言執行者の選任」を申立てる。(遺言執行者の選任も約1ヶ月を要する。)
↓
【3】定期預金の手続、不動産の名義変更の手続完了(およそ6ヶ月)
↓
【4】相続税の申告・納付(相続開始から10ヶ月が期限)
『遺言書の検認』を終えた後、家庭裁判所で遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は有効な遺言書で指名された姪Aとなり、Aが遺言執行者に選任されれば甲金融機関における解約手続きもスムーズに進むと考えられます。
仮に相続税の申告期限までに手続きが終わる見込みがない場合は、期限内に遺産が未分割として計算(法定相続分)した相続税の申告を行うことで、期限後申告によるペナルティ(加算税や延滞税)を防ぐことができます。
手続完了後に、実際の相続割合に応じた申告の修正を行いましょう。