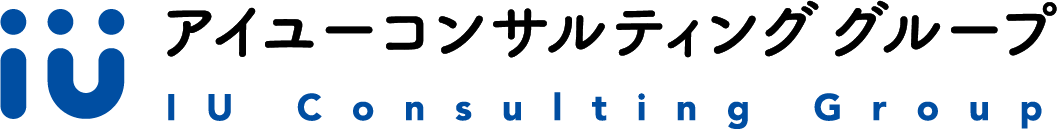贈与税は、無償で財産を譲り受けた(もらった)場合に、そのもらった人が納める税金です。同じ無償による財産の取得に対する税金でも、人の死亡を起因とする財産の取得に対して課税される相続税とは異なる税金になります。ただし、「生前贈与」という言葉があるように、相続税とは非常に関わりが深い税金であり、相続税の補完税としての役割を持っています。
もらった金額に応じて税率が上がるという累進課税を採用しているという点では相続税も贈与税も同じですが、贈与税の方が税率の上がり方が大きいという点には注意が必要です。
贈与税とは
いくらから贈与税がかかるのか
贈与税には、「基礎控除」という税金がかからない枠があります。
基礎控除の金額は財産をもらった人一人につき年間110万円であり、これは誰でも控除することができます。
したがって、1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円(※)を超えて財産をもらった場合には贈与税がかかるということになります。
※二人以上からもらっていればその合計が110万円を超えるかで判断します。
贈与税を納める人は誰か
贈与税は、財産をもらった個人(※)が納めます。
また、財産の贈与者(くれた人)や受贈者(もらった人)の住所や国籍が日本であるか否かなどにより、課税される財産の範囲が変わります。
※一定の場合には、特定の社団等も納税義務者になります。
贈与税がかかる財産とは
金品を問わず、経済的な価値を有するものはすべて贈与税の対象となります。
現金預金、不動産、有価証券などをイメージすると分かりやすいでしょう。
また、例えば親が掛金を負担していた保険の満期金を自分が受け取った場合のように、厳密にはそれ自体が贈与でなくても、贈与があった場合と同様の経済的効果がある場合については、税金の計算上は贈与があったものと「みなして」贈与税がかかることになりますので、思わぬ贈与税の発生には注意が必要です。
どのように評価額が決まるのか
贈与税の計算をする上で重要となるのが評価額です。
前述のとおり贈与税のかかる財産は多岐に渡ります。
現金であれば非常に分かりやすいのですが、不動産であれば現況や所在地、法的な規制や他人の権利の有無など、様々な要素を考慮して評価をする必要があり、有価証券であれば株式なのか投資信託なのかなどによって評価方法が変わります。
一般的には相続税と同様、国税庁が定める財産評価基本通達により評価額を計算しますが、例えば負担付贈与のように特殊な評価をする場合もあり、贈与の形態についても考慮する必要があります。
どのくらいかかるのか
父から1,000万円の現金をもらったAさん(20歳)を例に見てみましょう。
Aさんは1,000万円から110万円の基礎控除を差し引いた、残りの890万円に対して贈与税がかかることになります。
ここで注意が必要なのは「誰からもらったのか」という点です。
財産をくれた人が「直系尊属」(祖父母や父母)に当たる場合と、「直系尊属以外」(配偶者や叔父叔母など)に当たる場合とでは、税率が異なるためです(※)。前者を特例贈与、後者を一般贈与といいます。
※18歳以上の人がもらった場合に限ります。
上記の場合、特例贈与に該当するため適用される税率は30%となります。
なお、仮に配偶者から同額をもらった場合には一般贈与となるため適用される税率は40%となります。
どのように申告・納税をすればいいか
贈与税がかかることとなった場合、贈与税の確定申告期間中(贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日)に、税務署へ申告書の提出と納税をする必要があります。
まずは贈与税の申告書を作成する必要がありますが、もらった財産の用途などによっては、基礎控除に加えて一定の「非課税」や「特別控除」などを受けられる場合もあり、これに応じた申告書の記載と書類の添付が必要です。
申告の方法としては、紙による申告のほかに、e-Taxを利用した電子申告が可能です。
納税は納付書を使って金融機関等の窓口で納付するほか、クレジットカードによる納付やダイレクト納付による口座振替が可能です。
なお、上記の非課税や特別控除を利用する場合には納税額がなくても申告をする必要があります。