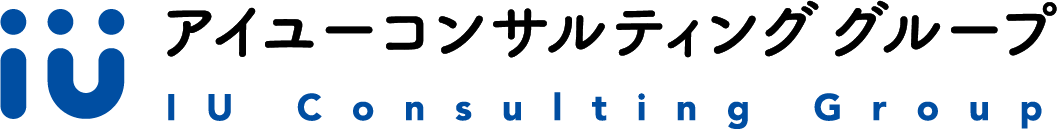相続後、どうしても不動産を売却せざるを得ないケースがあります。その際、不動産を売って得た利益は、所得税等と住民税の課税対象になります。
譲渡所得税の節税
譲渡所得税の節税例① 相続税の一部分を経費にする
相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。それによって売却益が減り、譲渡所得税の負担を軽減できます。
◆相続税の取得費加算の特例について
相続した土地や建物を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。取得費が増加することで譲渡所得が減少し、不動産譲渡に係る所得税等が軽減されるという効果があります。
◆相続税の取得費加算の特例の要件
相続や遺贈により取得した財産であること
その財産を取得した人に相続税が課税されていること
その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
譲渡所得税の節税例② 長期間所有している不動産を売却する
不動産の所有期間が5年超のものは、大きく税率が下がります。そのため利益が出る場合は、5年以内の短期所有売却は好まれません。
◆譲渡所得税率(譲渡した年の1月1日基準)
短期譲渡所得
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
長期譲渡所得
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
譲渡所得税の節税例③ 兄弟で住んでいた家屋を売却する
相続を機に自宅を売却する場合「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されます。
◆三人兄弟での売却の場合
三人兄弟が同居している自宅を法定相続分で取得後、売却して9,000万円の譲渡益が出た場合、登記持ち分に応じたそれぞれの譲渡益が3,000万円になります。そこからそれぞれ3,000万円控除を適用することができるため、譲渡所得税はゼロとなります。
◆注意点
長男が名義を全て取得し、弟二人に3,000万円ずつ現金で渡した場合には、自宅の売却をする際に長男の譲渡益9,000万円に対して、長男の3,000万円控除しか使えないため、利益が発生してしまい、譲渡所得税がかかってしまいます。
譲渡所得税の節税例④ 土地と建物の名義が違う場合、名義を贈与する
一次相続で土地は長男の名義になり、二次相続時に建物は妹名義、居住しているのは兄…などと、土地・建物・居住している人が入り組んだケースがあります。土地と建物の名義が違うと、兄は、売却した時に居住用財産の特別控除などを受けられず、多額の譲渡所得税を支払わなければならなくなることがあります。
◆解決策
妹から兄に建物の名義を売却する、もしくは一部を贈与する
そうすることで共有財産となり、将来売却することになったときに譲渡所得税の節税が可能になります。